(フィリップ・ピケット:リコーダー ニュー・ロンドン・コンソート 1990録音)
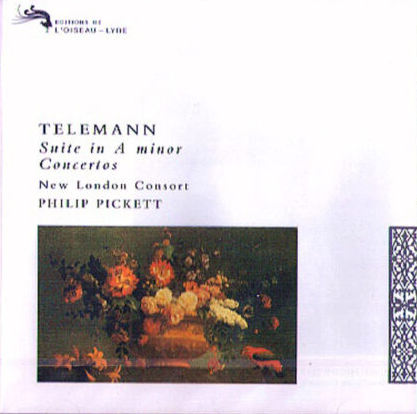
Amazon : Suite in a
テレマン/リコーダーと弦楽のための組曲 イ短調
(フィリップ・ピケット:リコーダー ニュー・ロンドン・コンソート 1990録音)
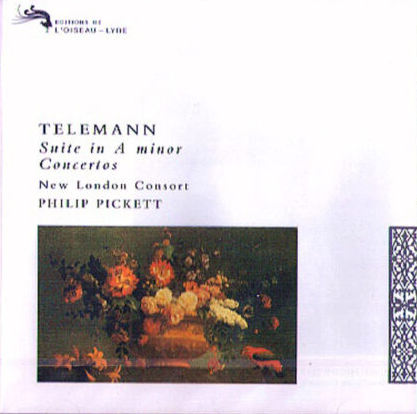
Amazon : Suite in a
「いきなりですけどね うちのオカンがね 好きな曲があるんやけど その名前をちょっと忘れたらしくてね」
「忘れたの? ほな俺がね ちょっと一緒に考えてあげるから どんな特徴かってのを教えてみてよ」
「なんかね、ドイツのバロック音楽で、木管楽器と弦楽のための組曲らしいんやわ」
「そらバッハ『組曲第2番』やないかい、ドイツ・バロックで木管と弦楽のための組曲言うたら、それはもう『組曲第2番』やわ」
「いや俺もバッハの『組曲第2番』と思うてんけどな」
「そうやろ?」
「オカンが言うには、横笛やなくて縦笛らしいんや」
「ほなバッハと違うかあー、『組曲第2番』はフラウト・トラヴェルソいうて横笛使うからなあ」
「あとオカンが言うには最初に長めの序曲があって、そのあとに短い曲がいくつか続くらしいわ」
「やっぱりバッハやないかい! 『組曲第2番』の構成そのものやないかそれ」
「それがなあ、その曲あんまり知られてなくて、たいていの人は聴いたことがないはずや言うんやわ」
「あー、それはバッハと違うかあー、『組曲第2番』はそうとは知らんでも誰でもいちどは聴いとるはずやからなあ」
バディネリ
(←聴いたことあるやろ?)
「ホンマに分からへんがなこれ」
「どうなってんねんもう」
・・・・・・はい、答えはゲオルク・フィリップ・テレマン(1681〜1767)のリコーダーと弦楽のための組曲 イ短調です!
バッハの「管弦楽組曲第2番」にほんとにそっくりなんですよ!
最初に長めのフランス風序曲(緩→急→緩)があり、そのあとに6つの短い曲が続きます。
序曲 (優美な名曲。 バッハ「組曲第2番」の序曲によく似てます)
喜び (活発な舞曲。中間部のリコーダーの技巧的な活躍!)
バッハとテレマンは友人だったので、どちらかがどちらかを真似したんじゃないかと思うくらいです。
作曲年代はテレマンの曲が1710年以前、バッハの曲は1720〜30年と推定され・・・ってことはバッハのほうが真似したのかな。
いまやバッハのほうが100倍くらい有名ですが、こういうのを「青は藍より出でて藍より青し」と言うのでしょうか。
しかしテレマンの曲も決してバッハに負けていません。
親しみやすいメロディに、軽やかに踊るリコーダー、キャッチーで聴いて楽しい傑作です。
ポロネーズ (バッハ「組曲第2番」のポロネーズに似てる!)
リコーダー奏者の間では知らぬ者なき有名曲らしいですが、一般的な知名度は低いです(テレマンの曲すべてに言えることですが)。
生前は絶大な人気と富に恵まれたものの、死後はバッハの陰に隠れてしまった感のあるテレマン。
もうちょっと広く聴かれてもいいのになあと思うのです。
序曲(ライブ)
(2023.02.19.)
その他の「テレマン」の記事
テレマン/無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲(ポッジャー独奏)
テレマン・エディション(「忠実な音楽の師」ほか)
テレマン/水上の音楽「ハンブルクの潮の満干」
テレマン/12のメトーディッシェ・ソナタ集