 |
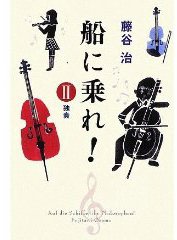 |
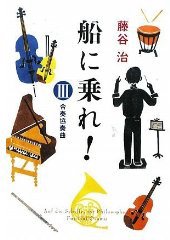 |
| 船に乗れ!〈Ⅰ〉合奏と協奏 | 船に乗れ!(Ⅱ) 独奏 | 船に乗れ! (Ⅲ)合奏協奏曲 |
| 船に乗れ! Ⅰ (文庫版) |
船に乗れ! Ⅱ (文庫版) |
船に乗れ! Ⅲ (文庫版) |
 |
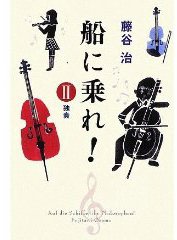 |
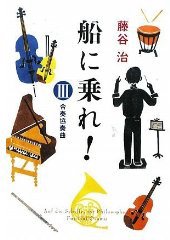 |
| 船に乗れ!〈Ⅰ〉合奏と協奏 | 船に乗れ!(Ⅱ) 独奏 | 船に乗れ! (Ⅲ)合奏協奏曲 |
| 船に乗れ! Ⅰ (文庫版) |
船に乗れ! Ⅱ (文庫版) |
船に乗れ! Ⅲ (文庫版) |
<ストーリー>
音楽一家に生まれチェロを学ぶ津島サトルは、藝高(東京藝大付属)を受験するも、あえなく失敗。
不本意ながら三流の新生学園大学附属高校音楽科に進みます。
ヴァイオリン専攻の南 枝里子との恋、夏休みのオーケストラ合宿、
市民オケのエキストラとしての初舞台、南とピアノの北島先生とのトリオ結成・・・、
甘酸っぱく輝いていたあの頃を、中年になったサトルが悔恨を込めて振り返ります。
(なお船員さんや漁師さんは一人も登場しませんので念のため。)
大傑作辛口青春音楽小説!!
力のある物語を読むと、心を乗っ取られてしまうことが、ままあります。
登場人物たちが心の中に住みついて、その後のストーリーを勝手に展開したり、サイドストーリーを語り始めたりするのです。
ここ3日ほど、この小説に完全に乗っ取られている私です。
藤谷治「船に乗れ!」
三流音楽高校を舞台に、生きることの辛さ・美しさ・醜さ・気高さを余すところなく描き出した、非常に「痛い」骨太青春小説です。
鼻もちならない主人公・サトルが痛い、自信と不安の間で揺れる南が痛い、先輩たちの俗物ぶりが痛い、教師たちの事なかれ主義が痛い。
でもどの登場人物もリアルで他人とは思えなくて、読みはじめたらやめられません。
「音楽家になる」という夢に向かって、ともに研鑽を重ねていたサトルと南。
しかし、ある出来事のために、二人の幸福な時間は永遠に失われてしまいます。
南の音楽を愛する心は、誰よりも強くまっすぐだったのに・・・。
むしろ「音楽を愛しすぎた」ことが、彼女の「悲劇」の一因とも言えるだけに、なおさら切なさがつのります。
結局のところ
「努力は報われるとは限らない」
「起きてしまったことはどうしようもない、なかったことになんかできない」
ということを思い知らされる小説なんですよねぇ(当然と言えば当然なんですが)。
将来ある若い人は読まないほうがいいんじゃない? と思うほどですが、いややっぱり滅茶苦茶面白いのでぜひ読んでほしいです。
ただし、ただいま青春まっただなかの少年少女には、ちょっとピンと来ないかも。
いろんなことをあきらめながら生きてきた大人の立場から、本気で願えば何でも叶うと信じていたあの頃を振り返る小説ですから。
心に多くの古傷・後悔・懺悔を抱える人ほど、ひりひりしみるメンソレータム小説。
私はウサギに唐辛子を塗られたカチカチ山の火傷タヌキのように七転八倒しましたよひいいいい!
さわやかなだけの青春小説とは、ひと味もふた味も違いますし、単なる音楽小説でもありません。
人生について、幸福について、愛することについて、読者に深く考えさせます。
ある意味哲学小説と言ってもよいくらいです。
とはいえ演奏場面の素晴らしさはやはり特筆大書もの。
第1巻で南とサトルが一緒に弾くメンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番の幸福な高揚感。
そして第3巻のクライマックスで鳴り響くブランデンブルク協奏曲第5番の華やかで哀しい名演奏。。。。
天才フルート少年伊藤慧、いつも明るいお姉さん的存在鮎川千佳、謎めいた美人ピアノ教師北島先生など
脇役たちも存在感大きなキャラばかり。
鮎川の心の中はどうだったんだろう、と考え始めるとそれだけでご飯3杯くらいいけそうです。
倫理社会の金窪先生の存在も忘れることはできません。
最後の最後まで素晴らしい講義をしてくれます、心して聴講したいものです。
実際、最終章にこの人が登場することで、タイトルの意味も明らかになり
物語にどっしりとした重みが与えられます。
全3冊の構成はきわめて音楽的。
ういういしく明るさあふれる第1巻(第1楽章)
陰鬱で哀しく、でもロマンティックな第2巻(第2楽章)
そして、先行楽章で提示された主題が絡み合う、ほろ苦くも華麗な怒涛のフィナーレ・第3巻。
ラスト近くで第1巻のメンデルスゾーンが「再現」するところでは、涙が眼幅で流れそうになります。
すべてを受け入れたあとに訪れた、南の「全部ありがとう」 サトルの「それでいい」 の境地は、この厳しい物語のいわば最終和音。
そして曲が、いや小説が終わってもまだ船は揺れ、航海は続くのです。
・・・現在の南が、平穏で幸せな日々を送っていることを祈らずにはいられません。
私的には今年読んだ本のベストですが、今年に限らず、10年、20年と読み継がれるべき名作の誕生ではないかと思います。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
小説の中で取り上げられた曲をいくつかご紹介。
黄色は本文からの引用です。
(ややネタバレ気味のため未読の方はご注意ください)
雪崩のような三連符、ピアノの分散和音、そして興奮の余韻を残す第一主題の展開。
南は明らかに僕を無視していた。あるいは無視している素振りをした。
トリオなんかじゃない、これはヴァイオリン・ソナタなんだと思って弾いていた。
がつんと来たな。それなら僕も、とチェロ・ソナタにピアノとヴァイオリンが伴奏しているつもりでがんがん弾いた。(第1巻262ページ)
↓
メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番(全曲)
あるのはメロディだけ、心優しく、もの哀しく、あらわれてたちまち消えていくメロディだけだ。(第1巻263ページ)
この美しい人に、ケンカをふっかけるのはどんなにたやすいことだろう、愛していると、本心を告げることにくらべれば。(第1巻264ページ)
↓
メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第1番・第2楽章
おじいさまがホーム・パーティーで弾いた曲
↓
バッハ:オルガン小曲集から「かくも喜びあふれる日」BWV605
バッハ:オルガン小曲集から「汝のうちに喜びあり」BWV615
「ヴァイオリンとチェロのための曲って、意外とあるみたいなの」
南は明るい口調でそういったけれど、息はまだ弾んでいた。
「先輩に詳しい人がいたから、訊いてみたの。ヘンデルのパッサカリアは、とってもいい曲なんだって。」(第2巻146ページ)
(たしかにいい曲ですが、哀愁と緊張に満ちた調べは、ふたりの恋の行方を暗示しているかにも聴こえます。
ふたりが演奏するこの曲を聴きたかった・・・。)
↓
ヘンデル(ハルヴォルセン編):パッサカリア(←サトルと南みたい?)
サトルにとっての「壁」になった曲。
易しい曲ではありませんが、ラフマニノフのチェロ・ソナタを弾けるサトルが歯が立たないというのは奇妙。
南の一件がサトルからチェロを弾く気力を奪ってしまったのでしょうか。
↓
バッハ:無伴奏チェロ組曲第2番ニ短調・クーラント
鮎川がどんなに練習し上達しても届かないものが、南のヴァイオリンにはあった。
最初の八分音符がわずかに震えただけで、彼女は堂々とソロを弾いて伊藤のフルートと、浅葉さんのチェンバロと渡り合った。
高音の伸び、十六分音符の切れ、上昇する音形の独特なクレッシェンド。
(中略)この気丈さ、図々しさ、たくましさは、天性のソリストにしか与えられないものだった。(第3巻160ページ)
↓
バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番・第1楽章
曲が進むにつれて、それは演奏でありながら、同時に饗宴になっていった。
もはやソロと合奏の区別もなく、音楽教育も、校則も、袖にいる教師たちも、文化祭もコンサートも観客もなかった。(第3巻168ページ)
↓
バッハ;ブランデンブルク協奏曲第5番・第3楽章
小説の最後を飾る2曲です。
「ジュピター」第4楽章の主要主題のひとつと、「ハフナー」第1楽章の締めのフレーズがそっくりなのですが、
藤谷さんはそれを意識してこの2曲を組み合わせたのかなあ。
↓
モーツァルト:ジュピター交響曲・第4楽章
モーツァルト:ハフナー交響曲
(09.11.21.)
音楽アンソロジー「Heart Beat」(JIVE 2008)には
「船に乗れ!」のスピンオフ短編「再会」が収録されています。
「船に乗れ!」から27年後のサトルと伊藤慧に会えます。
(注:ポプラ文庫版の「船に乗れ!Ⅲ」にも収録されています)
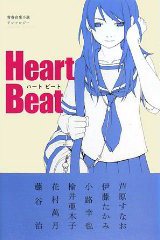
Amazon.co.jp : Heart Beat
追記:「船に乗れ!」ネタバレ&ツッコミ感想「船底の隅をほじくれ!」を追加しました(10.1.11.)