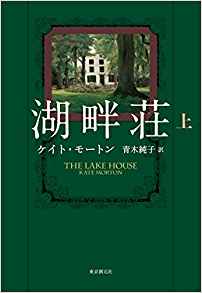 |
 |
| Amazon : 湖畔荘〈上〉 |
Amazon : 湖畔荘〈下〉 |
ケイト・モートン/湖畔荘
Kate Morton/The Lake House(2015)
(青木純子:訳 東京創元社 2017)
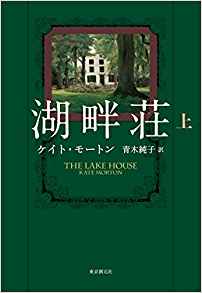 |
 |
| Amazon : 湖畔荘〈上〉 |
Amazon : 湖畔荘〈下〉 |
2003年、ロンドン警視庁の女刑事セイディは、若い母親が女児を置き去りにして失踪した事件で、
単なる育児放棄という上司の判断に納得がいかず、捜査情報を新聞社にリークしてしまった。
謹慎となりコーンウォールの祖父の家で暇を持て余すセイディは、森の中に打ち捨てられた屋敷・湖畔荘を発見。
湖畔荘では1933年のミッドサマー・パーティの夜に生後11か月の息子セオ・エダヴェィンが失踪し生死不明のまま迷宮入り、
エダヴェィン一家は辛い記憶に耐えられず、屋敷を放棄したのだった。
興味を抱いたセイディが調べるうち、仕事上の失敗と、セイディ自身の過去と、70年前の誘拐事件が交錯し始める。
いっぽう、エダヴェイン家の次女でセオの姉アリス・エダヴェインは、ミステリ作家として高い地位を築いていた。
親分:ケイト・モートン翻訳第4作「湖畔荘」だ。
ガラッ八:♪しずかな湖畔の森のかげから〜〜 「湖畔」と聞くとつい歌ってしまうでやんす。
親分:「リヴァトン館」 「忘れられた花園」 「秘密」・・・、過去と現在が交錯するトリッキーでアクロバティックな作風に磨きをかけてきた著者、
今回もびっくりな仕掛けで読者を驚かせてくれる。
ガラッ八:へえ、今回はどうなんですかい、教えてくださいよ、まだ読んでないけど。
親分:そんなもん読んでない人間に言えるかよ! とにかくびっくり仰天の大仕掛けだ。
一部で「ご都合主義」との声もあって賛否両論だが、面白いことは保証するぞ。
伏線の張りかたもじつに丁寧で、探偵役セイディの推理は二転三転する。
俺は最後に「なるほどそうきたか!」と思わされこそすれ、ご都合主義とは思わなかったけどな。
ガラッ八:しかしまあ、長いですよね。
親分:今回も安定の上下巻だな。
しかし文章はこなれていて読みやすいし、謎解き以外にも大戦間のイギリス上流階級の生活ぶりとか、面白かったぞ。
登場人物のキャラ造形も素晴らしく、とくにセオの母親エリナ・エダヴェィンの人物像には魅了される。
彼女こそこの物語の真の主人公だな。
ガラッ八:幼児失踪事件が起こった1933年を起点として、2003年と、1910年代の出来事がカットバック的に挿入されるんですね。
親分:いつものケイト・モートンの手法で、視点も目まぐるしく変わるが、読者が混乱しないように各章に年代が明記されている。
同じ出来事が、視点を変えると全く違う意味を持っていたことが明らかになるなど、「語りの超絶技巧」があちこちで炸裂している。
とはいえ、小難しいことはない、あくまでもエンタテインメント小説であり、上質のミステリだ。
冒頭付近と上巻の終わり近くで「ノックスの十戒」に言及しているのもフェアプレイ精神の表れだし、それ自体が伏線にもなっている。
ガラッ八:「ノックスの十戒」・・・推理小説を書くときのルールでしたっけ。
1.犯人は物語の最初から登場していなければならない。 2.探偵方法に超自然の力を使ってはならない。 3.犯行現場の抜け穴はどうたらこうたら、とかいうやつですね。
親分:それそれ、古い決まりで、あえてそれを破って書かれた傑作もたくさんあるが。
読み終えてから振り返ると、ケイト・モートン、この作品では「十戒」をきっちり守って書いてるんだな〜、遊び心だな〜。
ガラッ八:しっかり「本格」してるんですね。
親分:作家志望でのちにミステリ作家となるエダヴェイン家の次女アリスが、何でも観察しているようで、実はいちばん真実が見えてなかったというのも皮肉が効いている。
必要以上に陰惨だったり血なまぐさかったりせず、読後感が良いのは好印象。
エレガントな筆致ながら戦争の悲惨さは過不足なく描かれていて、作者のクレヴァーさを感じるなあ。
ある意味、戦争がもたらした悲劇でもあるわけで、いやホント、戦争はいかんよ・・・。
ガラッ八:あっしたちも仲良くしましょうね〜。
親分:気持ち悪いんだよ! 寄るなよ!
とにかく、今年の翻訳ミステリの中でもベスト級の大傑作である! 超オススメ!
(2017.11.04.)