(ロディオン・シチェドリン:ピアノ エフゲニー・スヴェトラノフ指揮 ソ連邦交響楽団)
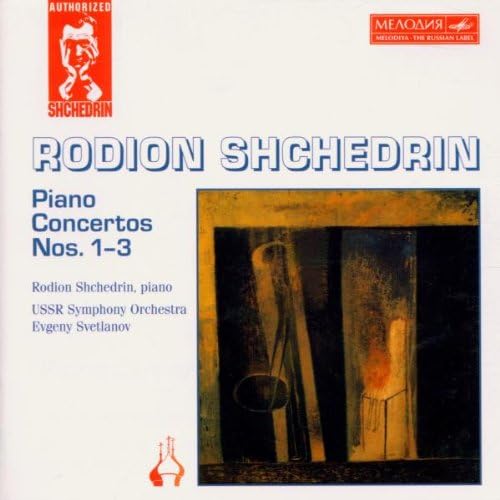
Amazon : Shchedrin Piano Concetos
シチェドリン/ピアノ協奏曲第1〜3番
(ロディオン・シチェドリン:ピアノ エフゲニー・スヴェトラノフ指揮 ソ連邦交響楽団)
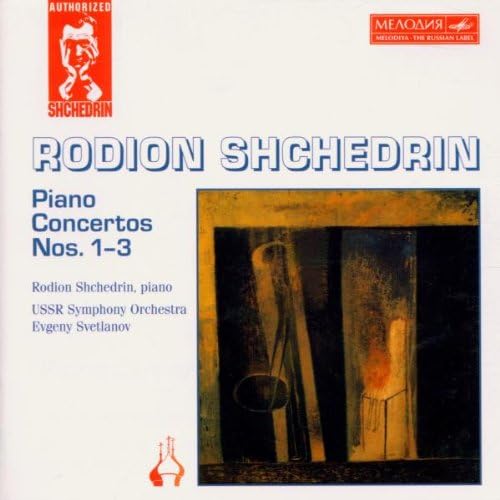
Amazon : Shchedrin Piano Concetos
ロディオン・シチェドリン(1932〜2025)が亡くなりました。
というか、まだ生きていたんですね(微妙に失礼)。
体制に従順なイメージがありましたが、1968年にはソ連のチェコスロバキアへの軍事侵攻を支持する署名を拒否したことで
モスクワ音楽院の教授を解職されています。
意外と硬骨漢だったのね。
妻のバレリーナ、マイヤ・プリセツカヤに頼まれてビゼーのオペラをバレエ用に編曲した「カルメン組曲」が有名ですが、代表作が編曲ものってのも気の毒な話。
オリジナル作品も魅力的です。
優れたピアニストでもあり、ピアノ協奏曲を6曲書いていて、そのほとんどを自分で初演しています。
一番有名なのはピアノ協奏曲第2番(1966)でしょうか。
12音技法や偶然性を取り入れた、かなり攻めた作品ですが、難解な作品を書くと「人民に寄り添っていない」と当局の不興を買ってしまうのがソ連時代。
多くの作曲家がそれで大変な目に遭いました。
そのあたりのバランスに苦労したことでしょうが、結果的に前衛性と大衆性が絶妙にブレンドされた大傑作となりました。
ジャズの技法も大胆に取り入れていて、カプースチンの先駆と言いたくなるほど。
第1楽章「ダイアローグ」
冒頭のピアノによる主題は12音からなります。
ピアノの長いモノローグのあと、3分すぎからオーケストラが本格的に加わり「ダイアローグ(対話)」が始まります。
基本的に無調ですが、取っつきにくいところはなく、ジャズっぽいノリの良さで耳を惹きつけ、飽かせません。
ひとしきり盛り上がったあと、8分くらいからふたたびピアノのモノローグとなり、静かにミステリアスに楽章を閉じます。
第2楽章「インプロヴィゼーション」は、スケルツオ風無窮動。
トランペットで呈示されるファンファーレ風な主題が様々に展開されます。
「インプロヴィゼーション(即興)」というタイトルが示すように、一部に偶然性が取り入れられているそうですが、聴いただけではよくわかりません。
サーカス風猥雑さと喧噪の中でピアノやオケの各楽器の超絶技巧を味わう楽章、カッコイイっす!
(作曲者自身のピアノ、メチャクチャ上手いな!)
第3楽章「コントラスト」は、静かな鐘の響きで始まります。
ピアノは4度と5度の和音を淡々と鳴らし続け、なんだか試し弾きでもしているみたい。
1分30秒からヴァイオリンが瞑想風の旋律を奏で、やがて管弦楽を巻き込んでいきます。
3分20秒からピアノが楽し気に飛び込んできて、軽やかなピアノと重厚なオーケストラがコントラストを成します。
ピアノはジャズっぽく走り回り、4分25秒からヴィブラフォンが加わることで完全にジャズになります。
重厚で威圧的な管弦楽と、軽妙で遊戯的なピアノの対照の妙。
最後は協調してリズミックに盛り上がり、全曲を閉じます。
このCDは第1番から第3番までのピアノ協奏曲を収めたもので、独奏はすべて作曲者自身。
ピアノ協奏曲第1番(1954)は22歳の時に卒業制作として作曲されました。
前年に死去したプロコフィエフへのオマージュかと思えるほどプロフィエフ風。
第4楽章 プレスト・フェストーソ
ピアノ協奏曲第3番「変奏と主題」(1973)は、33の変奏曲のあとに主題を呈示するという風変わりな単一楽章作品。
正直言ってちょっと取っつきにくいです。
1974年の初演では、作曲者が第1番から3番までのピアノ協奏曲すべてを一度に演奏し、センセーションを巻き起こしたそうです。
ご冥福をお祈り申し上げます。
(2025.09.30.)
関連記事
シチェドリン/カルメン組曲