(ジェルジ・パウク、澤和樹)
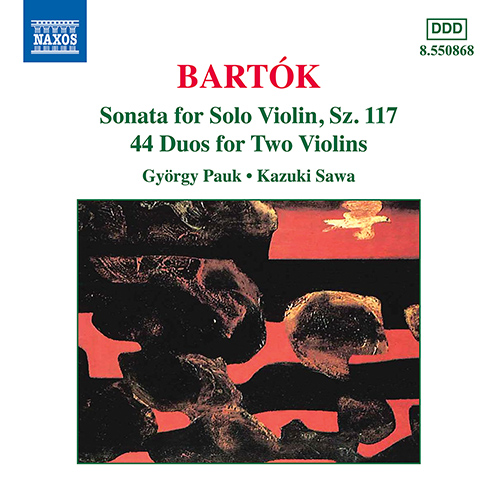
Amazon : Bartok 44 Duos
バルトーク/2つのヴァイオリンのための44の二重奏曲
(ジェルジ・パウク、澤和樹)
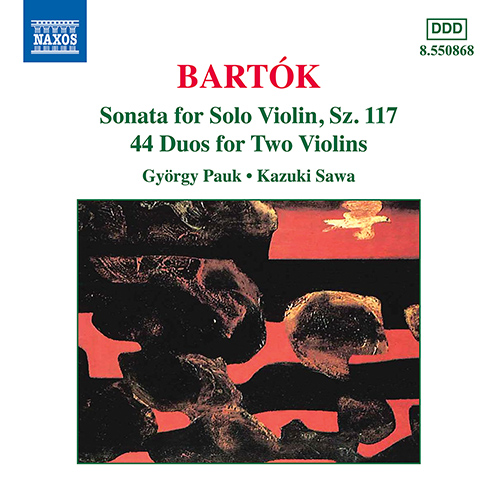
Tower : Bartok/44 Duos & Sonata for SoloViolin
Amazon : Bartok 44 Duos
かねてからベラ・バルトーク(1881〜1945)の音楽に近寄りがたいものを感じている私です。
知的で複雑で先鋭的で、いかにも頭のいい人が作った音楽って感じなのが気に入らねえ(←ほとんど言いがかり)。
そしてキビシイというか容赦がないというか、弦楽四重奏曲など聴いているとなぜか怒られているような気がしてくるんですよね。
私なんかがノホホンと生きててすみません〜って気になります。
つまり「なんとなく偉そうな音楽」という印象なのです(←完全に言いがかり)。
でも親しみやすい曲もあります。
2つのヴァイオリンのための44の二重奏曲(1931)
これなんか、可愛らしくていいですね〜。
ドイツのヴァイオリン奏者、教育者であったエーリヒ・ドフライン氏にヴァイオリン教本用の曲を依頼されたもの。
2つのヴァイオリンのための曲が44も並んでますが、1曲1分くらいなので40数分で全部聴けちゃいます。
簡単なものから徐々に難しくなっていくという寸法で、なるほど第1番は初心者でも弾けるかもしれません。
第1番 からかいの歌
第5番 スロバキアの歌 (ちょっと練習したら弾けそう?)
(このCDの演奏ではありません)
全体は4つの巻に分かれていて、だんだんと難しくなってゆきます。
第22番 モスキート・ソング(第2巻)
(このCDの演奏ではありません)
第29番 新年の歌その2 (第3巻)
(このCDの演奏ではありません)
第4巻ではかなりの技巧が要求されます。
第39番 セルビアの踊り(第4巻)
最後の第44番はこんな感じ。重音えぐい。
第44番 トランシルバニアの踊り
(このCDの演奏ではありません)
普通の練習曲集とは違って、東洋的で表情豊かで民族音楽の舞曲集のようなノリ。
じつは基本的に東欧の民謡を素材としていて、自作のメロディはほとんどないそうです。
バルトークは民謡の収集と研究を熱心に行っていましたから、その成果を利用したわけです。
彼は1906年から10年くらいかけてハンガリーのみならず、スロバキア、ルーマニア、さらにはアルジェリアまで足を延ばし、数万曲の民謡を集めました。
さらにそれらを分類・分析し、3万曲余りをまとめて「マジャル民謡大全」を作っています。
要するに
なんと蓄音機を持ち運び録音までしたそうです(20世紀初頭にこれはスゴイ)。
でも農民たちは役人が何か調べに来たのかと思い、
さて、この2つのヴァイオリンのための44の二重奏曲、面白いことに、技術的に難しい曲から先に書き、だんだんと易しい曲へと移っていったそうです。
演奏上の容易は作曲上の困難。
超絶技巧の曲よりも、シンプルで聴き応えのある音楽を作るほうが難しいんですね。
CDはいろいろ出ていますが、東京藝術大学第10代学長・澤和樹先生によるナクソス盤を。
(2022.12.3.)
その他の「バルトーク」の記事
バルトーク/弦楽のためのディヴェルティメント