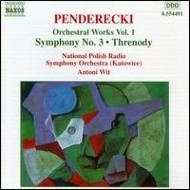
Amazon.co.jp : ペンデレツキ:管弦楽曲集(1)
HMV : Penderecki/Symphony No.3
ペンデレツキ/交響曲第3番、広島の犠牲に捧げる哀歌 他
(ヴィト指揮 ポーランド国立放送カトヴィツェ交響楽団)
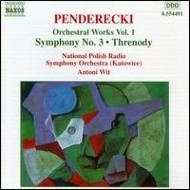
Amazon.co.jp : ペンデレツキ:管弦楽曲集(1)
Tower@jp : Penderecki: Orchestral Works Vol 1 / Antoni Wit, Polish RSO
HMV : Penderecki/Symphony No.3
ポーランドの作曲家・ペンデレツキ(1933~2020)といえば、代表作「広島の犠牲に捧げる哀歌」(このCDにも収録されてます)の
ギンギン前衛・ギラギラ過激なイメージが強烈で、ほかの曲には手が伸びなかったのです。
ペンデレツキだかキツネツキだか知らないが、好みの作曲家じゃないなあと。
しかし、ペンデレツキは、70年代後半から、ネオ・ロマンティシズムと称し、調性やメロディのある作品を書くようになったのだそうです。
その代表作、交響曲第3番はとても面白く聴ける傑作だということで、こわごわ聴いてみました。
1988年から95年にかけて作曲されたそうです。
第1楽章は、サスペンス・ホラー映画の幕開けのような短いイントロダクション。
怪しい足音のような低音弦、管楽器やヴァイオリンがミステリアスな雰囲気を盛り上げます。
「なにかがそこにいる・・・」と、ナレーションが聞こえてきそう。
ま、「エクソシスト」「シャイニング」の音楽を担当した人ですからね。
第2楽章は、「春の祭典」ふう原始エネルギー噴出系・アレグロ・コン・ブリオ。
めまぐるしく変わる楽想がとても面白く、怪獣が暴れているような感じです。
トム・トム、ボンゴなどの打楽器群が大活躍(5分30秒)、各楽器の技巧的なソロも多く、退屈する暇もありません。
いやあこれは興奮します。元気でます。
第3楽章はマーラー風に始まるアダージョ。
叙情的でノスタルジックなヴァイオリンの歌、慰めるようにからむ管楽器、ほとんどロマン派です。
良いのでしょうか、こんなに手放しに美しくて。私は好きですが。
第4楽章「パッサカリア」。
低音弦による二音の同音反復の上に、他の楽器が次々重なってゆき作り上げられる音の大伽藍。
頂点で力を失って静まり、バス・トランペットとイングリッシュ・ホルンの旋律が「お告げ」のように響き渡ります。
第5楽章はリズミックなフィナーレ。
荒っぽいリズムパターンの上に、いろいろな楽器が現れては消えてゆく、賑やかでエネルギッシュな楽章。
第2楽章と似た雰囲気ですが、この楽章は「怪獣大行進」と呼んであげたい。
そういえば、ノリのよさでは伊福部昭の音楽と共通する部分もあるような気が。
さまざまなアイデアを惜しげもなくつぎ込んだ、聴きごたえのある交響曲でした。
だてに作曲に7年もかけていませんね。 楽しく聴かせていただきました。
さて、このCD、余白に「広島の犠牲に捧げる哀歌」「フローレセンセス」「ドゥ・ナトゥーラ・ソノリスⅡ」の3曲が収められています。
どれも初期の、前衛まっしぐら時代の産物であり、集中して聴くのはちょっと苦痛でありました。
これまでにない新しい音響をいかに作り出すか、その限界に挑んだ力作ぞろいではありますが。。。
有名な「広島の犠牲に捧げる哀歌」(1960)は、最初は『哀歌、8分26秒』というタイトルだったそうです。
その後、ポーランドのオーケストラが日本に演奏旅行に行く際に、この曲も演奏されることに。
それではというので、タイトルを「広島の犠牲に捧げる哀歌」に変更したのだそうです。
テ、テキトーすぎませんかそれって!?
ペンデレツキにしてみれば、新作を原爆の犠牲者に捧げることで哀悼の意を表したつもりだったのでしょうが・・・
結果的に、この曲はペンデレツキの名を世界にとどろかせました。
それには、この刺激的なタイトルも多少は影響したはず。
なんか利用されたみたいで、日本人としては心境複雑であります。
52の弦楽器のための、特殊奏法満載の「響きの冒険」として、タイトルにとらわれずに聴いたほうが良いかもしれません。
(07.4.30.)