(ヤン・ヴィレム・デ・フリーント指揮 NDR放送交響楽団)
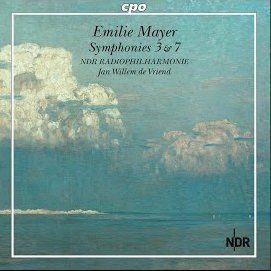
Amazon : Mayer Symphonies No.3 & 7
エミーリエ・マイヤー/交響曲第3番「軍隊風」&7番
(ヤン・ヴィレム・デ・フリーント指揮 NDR放送交響楽団)
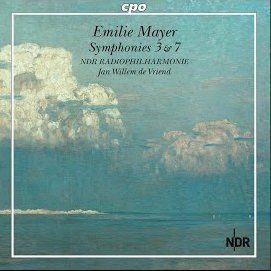
Amazon : Mayer Symphonies No.3 & 7
1840年、プロイセン王国(現在のドイツ)のフリートラントという町で、ヨハン・アウグスト・フリードリヒ・マイヤーという資産家が亡くなりました。
財産を受け継いだのは28歳で独身の長女、エミーリエ・マイヤー(1812〜83)。
エミーリエは莫大な遺産を何に使ったかというと・・・・。
音楽に全振りしました!
1841年にシュテティーン(現在のポーランド、シュチェチン)へ居を移し、同市の音楽界の中心人物であったカール・レーヴェ(バラードの作曲で有名)に師事。
1847年に交響曲第1番と第2番がシュテティーン器楽協会で好評を博すと、恩師の後押しもあり大都会ベルリンへと進出します。
ベルリンでもさまざまな音楽家に師事しながら自費で自作の出版を開始。
豊富な財産にモノをいわせてみずからコンサートを企画しては自作を披露します。
なんともエネルギッシュな女性ですね〜。
交響曲第3番ハ長調「軍隊風」は、1850年に自身のコンサートで初演して好評だった作品。
ハイドンや初期ベートーヴェンを彷彿とさせる・・・というか言ってしまえばモロに模倣です。
ウィーン古典派の音楽じゃないですかこれ! 1850年ですよ!
タイトルの由来となった第4楽章は、クラシックファンに作曲者を伏せて聴かせたら「ハイドンだね!」と答えること間違いなし。
でも手法は手堅く、ポップで歯切れが良くて洒落ていて、聴衆にはけっこう受けたそうです。
メンデルスゾーン、シューマンといった同時代の天才たちと比較しては気の毒ですが、かなり楽しめます。
第4楽章
交響曲第7番ヘ短調(1856)はさらに進歩しています。
古典派の枠組みからは脱し、前期ロマン派のドラマチックな緊張感と洗練を我がものにしています。
メンデルスゾーンの模倣と言ったらそうかもしれませんが、当時流行っていた一般的な管弦楽手法に従ったらこういう曲になるのでしょう。
キャッチーなメロディが連続、聴くものを飽きさせない、レベルの高い傑作です。
個人的にはメンデルスゾーンの第1番には勝ってるんじゃないかと思いますね、いやほんと。
第1楽章
エミーリエ・マイヤーはプロイセン王妃から「芸術の金メダル」を授与されたり、
自作を紹介するためにケルン、ミュンヘン、リヨン、ブリュッセル、ウィーンに演奏旅行もしました。
8曲の交響曲、7曲の弦楽四重奏曲をはじめとする多くの室内楽曲、ピアノ協奏曲1曲、管弦楽序曲15曲、多数のピアノ曲、そしてオペラをひとつ残しました
しかしベルリン以外で彼女の曲をすすんで演奏しようという演奏家や団体はあまりおらず、もっぱらセルフ・プロデュースのコンサート頼み(金かかっただろうな)。
そのせいか死後、作品が演奏されることはほぼなくなり急速に忘れられます。
もちろん女性だからというのはあったでしょう。
音楽家デビューが遅く、音楽一家の生まれでもないため、有力な人脈を持たなかったこともハンデでした。
それでもこの人の音楽的センスは超一級だと思います。
ただ当時の音楽型式・表現の枠内にとどまり、それを打破しようとか前進させようという意欲は感じられません。
多少でも破天荒で型破りなところを持ち、独自の個性を発揮できていればと思いますが、そこが天才と秀才を隔てる壁なのか。
まあ生前はベルリン音楽界で重要な地位を確立し、大家として扱われたそうで、ご本人としては満足な人生だったのではないでしょうか。
それにしてもエミーリエ・マイヤーの忘れられっぷりはかなりのものでありまして、
女性作曲家を扱った書物として有名な小林緑「女性作曲家列伝」(1999)にも登場しません。
彼女の作品が録音され始めたのは21世紀に入ってからで、2010年以降じわじわと名前が知られるようになってきているようです。
(2025.07.05.)