Anna Kavan/ICE
(山田和子・訳 ちくま文庫 2015年)
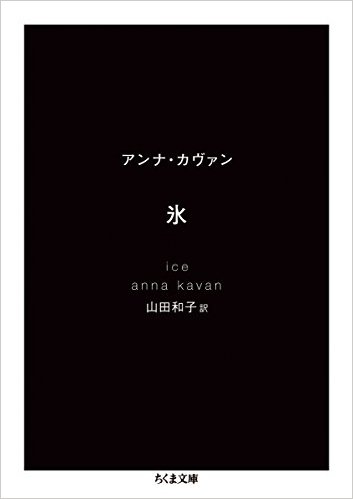
Amazon.co.jp : 氷 (ちくま文庫)
アンナ・カヴァン/氷 (1967)
Anna Kavan/ICE
(山田和子・訳 ちくま文庫 2015年)
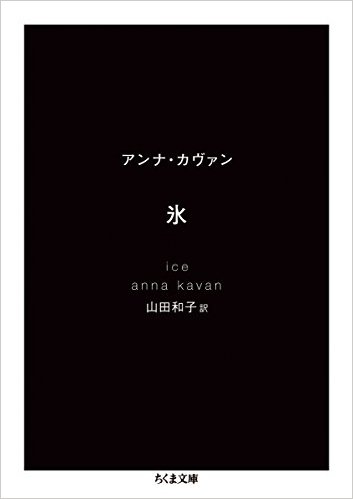
Amazon.co.jp : 氷 (ちくま文庫)
氷が全世界を覆いつくそうとするなか、逃れるように姿を消した「少女」を追う「私」は、
戦争に明け暮れる世界の中で絶対的な力を振るう「長官」と対峙する。
権力を駆使して「少女」を支配し保護する「長官」。
「少女」を取り戻すために二人を追い求める「私」、迫り来る氷の壁、略奪と殺戮。
恐ろしくも美しい終末のヴィ ジョンが、冷たい熱狂を引き起こす伝説的名作。
いやー、暑いです。
最高気温が36度とか37度とか、狂っているとしか思えません。
せっかくの祝日ですけど、頭のお皿が干上がってしまいそうで出かける気にもなれません。
ここはひとつ冷たくて厳しい小説でも。
アンナ・カヴァン/氷 (1968)
ストーリーは整合性ゼロ。
というかそもそもストーリーはあるのだろうか。
なぜ氷が世界を覆い尽くそうとしているのかは説明されず、誰が誰と戦争しているのかも説明されず、
なぜ「私」が「少女」に執着するのかも説明されず、なぜ「長官」が少女を支配するのかも説明されません。
場所も時代もわからないし、登場人物には名前がありませんし、「私」はモラハラでDVだし、「長官」は「ラピュタ」のムスカみたいです。
「少女」は戦争に巻き込まれて死んだり、怪我をしたりしますが、ページをめくるとまた別の街で長官と滞在していたりします。
「少女」が死んだのは「私」の妄想あるいは夢という解釈なのでしょうか。
それを言うならこの小説全体が悪夢または幻想を美しく文章化したような代物です。
登場人物たちは氷の迷宮を彷徨い続け、世界は永久に閉ざされます。
全編を覆う不安感・疎外感・暴力性・妄想性・不条理性・・・、読んでるうちに「こいつらみんなヤバイ」と確信せずにはいられません。
それでいて読むのをやめられません。
アンナ・カヴァン(1901〜1968)は、フランスで生まれ、イギリスで亡くなった作家・画家。
長く精神を病み、ヘロインの常用者であり、死体が発見されたときもかたわらにはヘロインの注射器があったと言います。
「氷」は、カヴァン最後の長編小説で、最高傑作とも言われます。
氷が世界中を覆い尽くすといっても、単純に気温が下がって寒くなるのではなく、巨大な氷の塊が物理的に北から南から押し寄せてくるのです、この世界では。
非常に涼しげなイメージでありまして、地球温暖化に悩み猛暑にあえぐ今の我々にはいっそ魅力的にすら映りますが、
やっぱり何読んでも暑いものは暑いですねえ・・・。
(2016.08.11.)
虹色の氷の壁が海中からそそり立ち、海を真一文字に切り裂いて、両方に水の尾根を押しやりながら、ゆるやかに前進していた。
青白い平らな海面が、氷の進行とともに、まるで絨毯のように巻き上げられてゆく。
それは恐ろしくも魅惑的な光景で、人間の眼に見せるべく意図されたものとは思えなかった。
その光景を見降ろしながら、私は同時に様々なものを見ていた。
私たちの世界の隅々までを覆いつくす氷の世界。
少女を取り囲む山のような氷の壁。 月の銀白色に染まった少女の肌。
(212ページ)